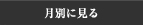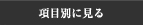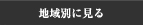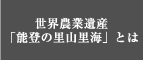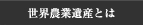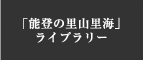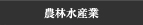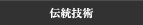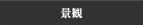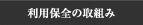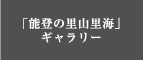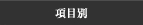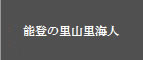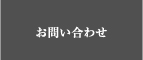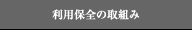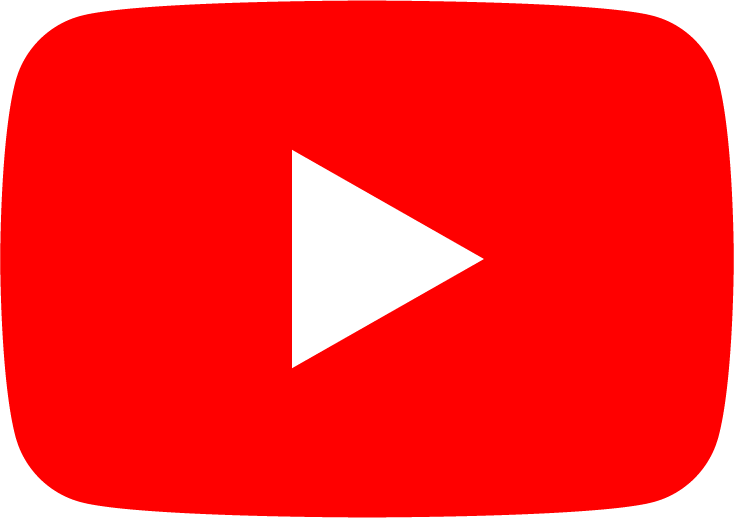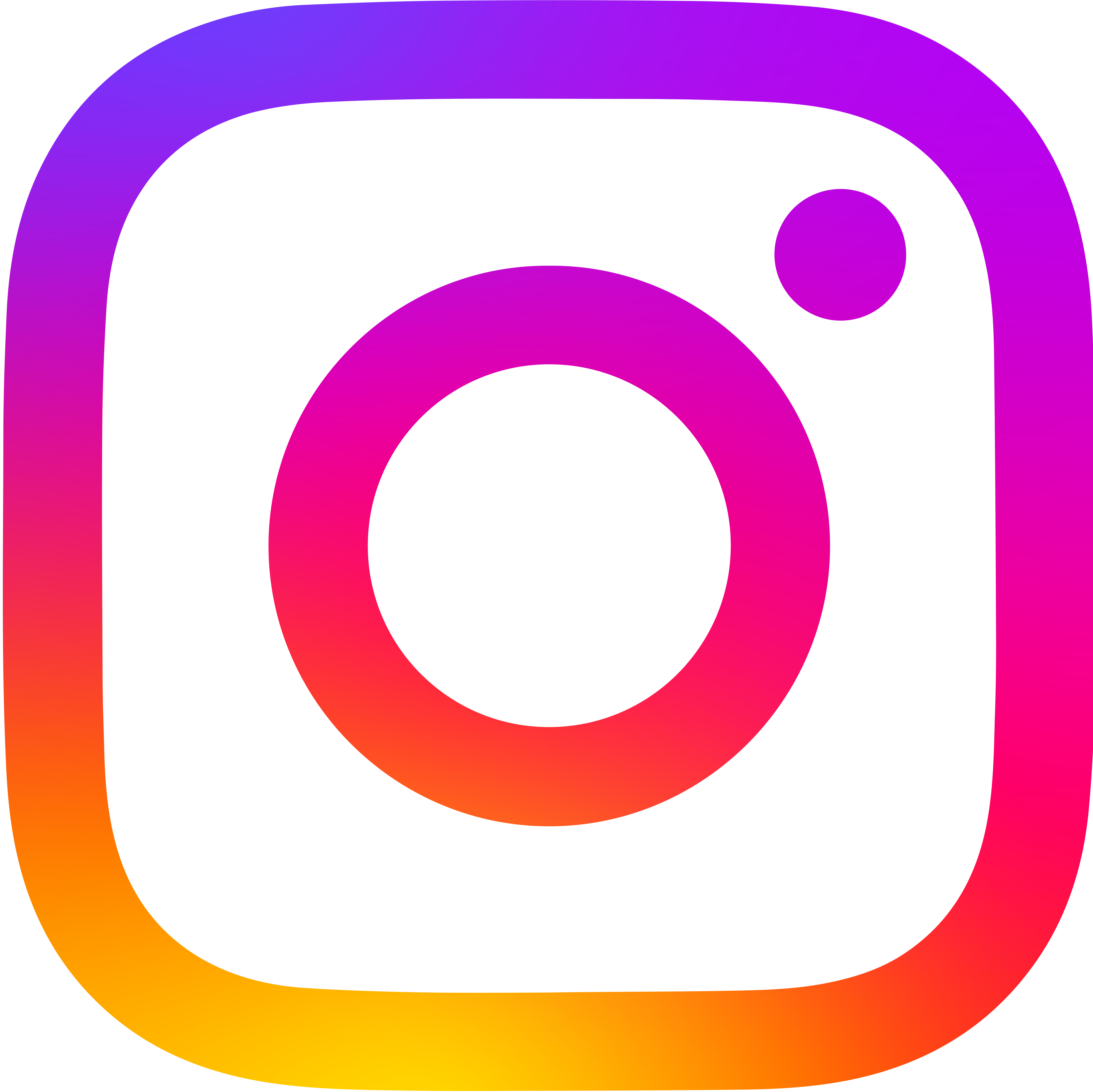|
HOME>世界農業遺産「能登の里山里海」ライブラリー>農林水産業>歴史的かんがい施設>用水路 農林水産業>歴史的かんがい施設用水路(1)概要及びGIAHS的価値について新田開発とは、山野や湖沼を開拓し、田畑にすることである。全国的には、江戸時代のはじめからおよそ100年間で、田畑が2倍近くに増えたといわれている。能登を支配した加賀藩も、寛永4(1627)年以降、新田開発を奨励し、米や畑作物の生産高の増加をはかった。能登における新開高の増加率は、貞享元(1684)年で22%、正徳元(1711)年で28.9%となっている。
能登は、山地、河川、海岸などの様々な態様があり、地形が複雑で、かんがい条件も多様であるが、概して用水不足を訴えるところが多かった。能登の農民は、用水を確保するため、困難な地形条件を克服し、自然の猛威と対しながら、用水路やため池などのかんがい施設を構築し、300年以上にわたり、守り続けてきた。
輪島市鵠巣地区では、塚田川を取水口とする「春日用水」が築造され、稲舟台地を潤している。七尾市の旧田鶴浜町舟尾村では、新田開発の折、全長700mのかんがい水路が築造され、中間部の高ノ山の下には、「マンポ」と呼ばれる地下水路がつくられている。また、七尾市の旧深見村にも、全長約300mに及ぶ巨大な地下水路「深見村マンポ」がある。
用水は農業の死命を制する。それだけに、農民は、用水の確保に懸命であった。日照りの際は、用水をめぐり、しばしば、同じ用水路から取水する隣村同士の争いがみられた。
輪島市鵠巣地区では、塚田川から取水する春日用水が築造されたが、用水の末端にあたる大野村と上流の水を共有する久手川村では、水争いが絶えなかった(後述)。当初は、日照りになると、3日のうち半日だけ配水を止め、水を送るという慣行が守られていたが、明和年間(1764〜1772年)には、慣行を無視し、勝手に振り水するようになり、大野村の人々の不満は、130年後の明治27(1894)年の訴訟にまで続くこととなった。 また、輪島市打越を流れる尾山用水は、樋ノ口山の水持林を水源としているが、山の木を伐ろうとする惣領と、水持林を水源とする尾山用水を守ろうとする打越や明崎の争いも、寛保2(1742)年から明治にいたるまで続いた。
能登における農業生産の増加の背後には、用水をめぐる、長きにわたる隣村同士の争いもみられるが、用水の管理が、運命共同体ともいえる強力な地域コミュニティを生む契機になったともいえる。輪島市惣領では、膨大な費用と労力をかけ、大江用水が築造されたが、管理のために、極めて厳格な番水制が施かれていた。番水を守らない者に対する細かい罰則も設けられていたことが確認されており、地域コミュニティによる自治を育んだともいえる。
また、用水路は、両生類や魚類、昆虫類などの生息場所となる水田やため池をつなぐ役割を果たし、それらと水のネットワークを形成し、多様で広域的な生物の生育環境を提供し、生物多様性にも寄与している。
(2)背景(経緯〜現状)能登の用水やため池などのかんがい施設の築造年代は、明らかではないものも多いが、鎌倉時代にはすでに新田開発が行われていた記録がみられ、藩政時代初期から大規模なかんがい施設が築造されていったと考えられる。
歴史的にもっともかんがいに苦しんだといわれる輪島市鵠巣地区には、塚田川を取水口とする春日用水が流れ、稲舟台地を潤し、大野村から海へ注いでいる。稲舟台地には、ひとつの伝説がある。建仁年間(1201〜1203年)のある日、笠原藤太という人物が、干からびた田を眺めながら、「この田へ水を入れてくれる者がいたら、一人娘をやってもいい。」とつぶやいていると、どこからともなく一人の若者が現れ、一晩のうちに田に水を満たした。しかし、この若者の正体は大蛇であったため、おそれをなした藤太が家に閉じこもっていると、大蛇が鍵穴からもぐり込んできた。その時、飼っていたカニが出てきて、大蛇を9つに切ってしまったという。水に苦労していたこの地域の暮らしがうかがえる伝説である。
春日用水は、下村兵四郎という人物が、舟に乗って沖に出て、地面の高さを目測し、造ったと伝えられている。また、輪島市打越を流れる尾山用水も、兵四郎という人物が測量したと伝えられる。下村兵四郎は、寛永4(1627)年から9年間、奥能登支配を担当した稲葉左近の指揮下にある代官であった。下村兵四郎は、金沢城下の築造にたずさわり、金沢城や兼六園の水を確保する辰巳用水を完成した板屋兵四郎と同一人物であるとする説もある。
七尾市旧田鶴浜町では、安政年間(1854〜1859年)に、舟尾村の肝煎をつとめた左近四郎(大橋家12代当主)が、検地、田地割などの測量をつとめ、用水である舟尾川やマンポをつくったといわれている。
これらの事例から、高度な土木技術を保持していた加賀藩の役職にあった人物や村のリーダーが、能登における用水の築造にたずさわったと考えられる。慶安4年(1651年)、加賀藩は、「改作法」を実施し、主要な用水の管理機構は、郡奉行による管理から改作奉行の支配となり、以下、十村衆、村肝煎、井肝煎という体系ができあがった。特に、井肝煎は、取水から配水にいたる一切の実務を専任したため、公平性と公明性が求められた。このため、用水受益の村々から出されるとは限らず、場合によっては、受益以外の村から選ばれることもあった。
明治維新は、用水の管理組織に大きな変革を与えた。十村は、郷長もしくは戸長に、村肝煎は、村長に組み替えられ、それまで用水を中心に組織され運営されてきた郷村社会は、村寄合的性格が否定され、官治的性格を強めた。明治11(1878)年、郡区町村編成法などにより、各用水は「江下町連合会」を組織し、用水の管理運営にあたったが、実質の運営は、旧藩政時代と大差はなかった。明治21(1888)年の市制、町村制により、強力な地方組織(官治機構)が確立されたが、水利関係地域とは無関係に編成・統合されたため、水利組合が結成された。明治41(1908)年には、水利組合法が制定され、組合は、用水管理者としての機能を維持し、運営されてきた。
戦後、占領軍総司令部の命令により、農地改革が行われ、地主制度が廃止され、土地は各コミュニティの小作人に再分配された。昭和24(1949)年には、土地改良法が制定され、水利組合は廃止され、耕地整理組合と統合して、土地改良区という組織へ一本化された。土地改良区は、現実の農村社会において、伝統的な農村地域社会と密接な関わりをもつ組織である。構成員は、耕作農民であり、事業費、管理費は、組合員が負担する。
用水路は、農業用水としてはもちろん、飲料水や防火用水としても利用されている。かつては、農業の死命を制するといわれた用水であるが、戦後の稲作生産の抑制、人口減少と高齢化による農業人口の減少などにより、その使命や利用法も変わりつつある。近年は、農業用水を利用した小水量発電などでも注目を集めている。
(3)特徴的な知恵や技術輪島市鵠巣地区の春日用水は、百文山の裾野を、ほぼ90mの等高線に沿って延びており、勾配200分の1以下と思われる緩やかな流れである。七尾市の旧田鶴浜町舟尾村で、新田開発の折、築造された全長700mのかんがい水路の中間部の高ノ山の下には、「マンポ」と呼ばれる地下水路がつくられている。舟尾川のマンポは、大小二本の地下水路からできており、中間部は「くの字」に折れ曲がり、増水時、水の流れを調整するようになっている。七尾市の旧深見村にも、全長約300mにも及ぶ巨大な地下水路「深見村マンポ」があるが、このマンポは、山にゲタ舟と呼ばれる舟をつきあて、両側から土砂を舟の上に落として、埋め立て地に運ぶことによりつくられたといわれている。これらから、築造当時、能登には、高度な土木技術、それを施工する土木指導者もしくは土木技術集団があったと推察できる。
(4)生物多様性との関わり用水路は、生物多様性への寄与も確認されている。水田やため池は、両生類や魚類、昆虫類などの生息場所ともなっており、用水路は、それらをつなげる役割を果たしている。用水路により、ため池から水田、河川から水田、上流から下流、さらには、海へとつながる水のネットワークが形成され、動植物は、川やため池、水田、海の間を移動することができ、多様で広域的な生物の生育環境となっている。
(5)里山里海との関わり能登では、ため池や用水路などのかんがい施設の築造と維持、管理は、共同体単位で行われてきた。渇水時には、近隣や隣村との水争いもあったが、厳しい自然と共存していくため、公平で公明な番水が行われ、用水単位で共同体が育まれてきた。共同体は、運命共同体でもあり、強力な結束力をもって運営され、キリコ祭りなどの独特な文化も育んできた。
<参考文献> 図書・報告書
|
 |
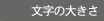     Loading
|