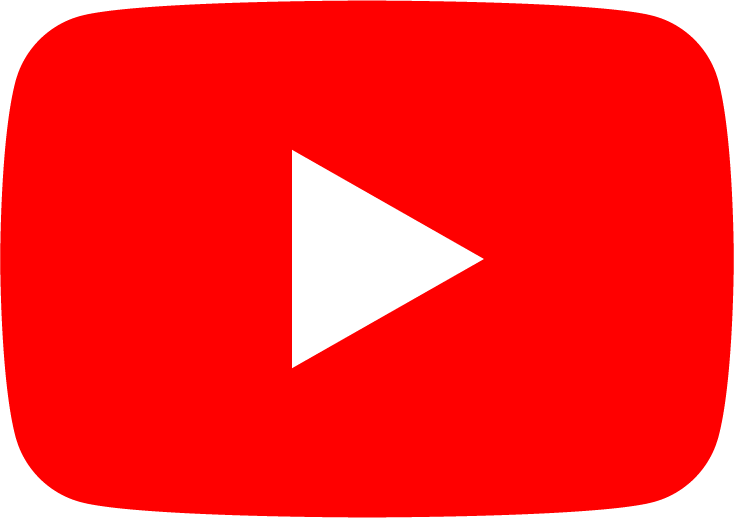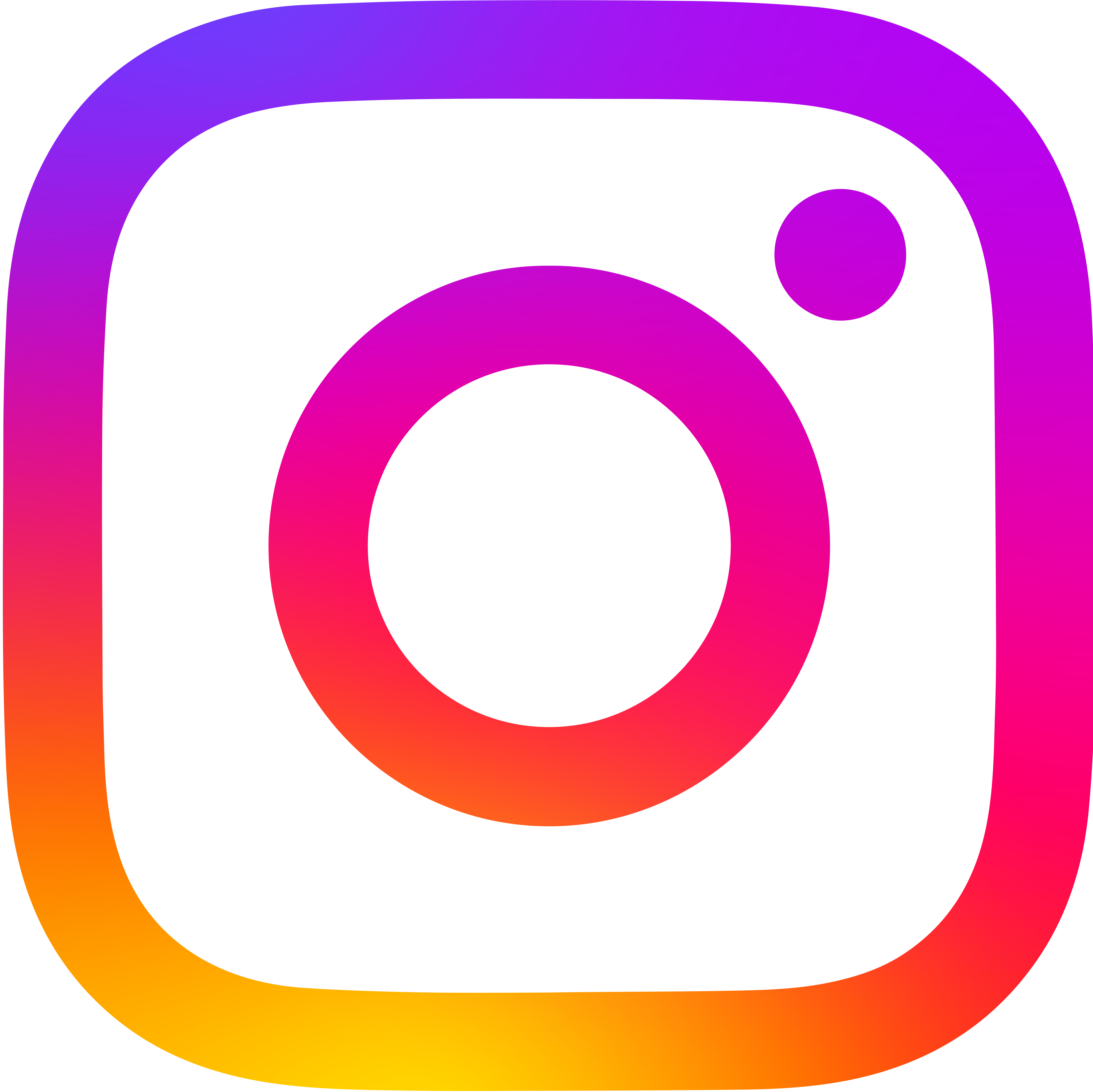|
HOME�����E�_�ƈ�Y�u�\�o�̗��R���C�v���C�u�����[���`���Z�p���`���H�|��`���Z�p�����C�̓`���Z�p �`���Z�p���`���H�|��`���Z�p���C�̓`���Z�p�i1�j�T�v�y�тf�h�`�g�r�I���l�ɂ����@�\�o�̗��C�̑�\�I�ȓ`���Z�p�Ƃ��āA�g���l����������������B��F�s�𒆐S�Ƃ����O�Y�̊C�ݐ��ł́A�_�k�n���R�����A�_���ɂ�艖�Â��肪���ƂƂ��đ������Ă����B���̓`���I�ȉ��Â���̕��@�́A�����ł͎�F�s�݂̂Ɍp������Ă���A����20�i2008�j�N�ɂ́A��F�s�p�ԉƂ́u�\�o�̗g���l�������̋Z�p�v���A���̏d�v���`�����������Ɏw�肳�ꂽ�B
�@�Y�ƂƂ��Ă̐����́A����38�i1905�j�N�̉��ꔄ���̎��{�A�����̋ߑ㉻�Ȃǂɂ��A�ꎞ�r�₦�����̂́A����9�i1997�j�N�A�ꔄ�����p�~���ꂽ���ƂŁA�n��̓��Y�i�Â���Ƃ��āA�g���l���̉��Â�������铮��������ɂȂ����B
�@���Â���ɂ�����Z�p�҂ł���u�l�m�i�͂܂��j�v�́A��ォ�狳������m�������ƂɁA����o����ς݁A�Z�p���K������B�g���l�������̌����͊C���ł���A���C�Ɣ��ɂ�����肪�[���Y�Ƃł��邪�A�q�����̔R���ƂȂ�d���v��I�ɒ��B����K�v�����������Ƃ���A���R�Ƃ������������B�l�m�́A���R���C�̕ω���q���Ɋ����Ƃ�Ȃ���A���Â�����s���Ă����B �@�@�ʐ^�@�@���c���i�i�p�ԉƁj�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������
�i2�j�w�i�i�o�܁`����j�@�ΐ쌧�̊C�݉����̒n��ɂ����鐻���̗��j�́A��2��N�O�ɑk��B�l�Êw�����ɂ��ƁA�Õ�����i250�`583�N�j�ɂ́A�\�o�����͐��˓��n���ƕ��сA�����̒��S�n�ł������B
�@�]�ˎ���ɂ́A�u���l���v�ƌĂ��A���ɉ�����t�������邽�߂ɁA���̊����𗘗p���ĉ��c�ɊC�����������݁A�����̎悷����@����������A��Ƃ̏ȗ͉����͂���ꂽ���A�\�o�ł́u�g���l���v���p�������B�u�g���l���v�́A���̏�ɐl�͂ŊC�����U�z���A�V���Ő��������������Ă����̎悷��A�d�J�����Ƃ��Ȃ����@�ł��邪�A�\�o�ł́A���n�������铙�̒n�`�����ɉ����A�C������A����ɂ́A���̊����̍������Ȃ����̎��R�����̂��߁A�u�g���l���v���p�������ƍl������B
�@�ː����ɂȂ�ƁA����˂́A������˂̐ꔄ���ɂ����A�u����āv�Ƃ������x�Ŕ\�o�̐��������サ���B�u����āv�́A�˂��O�����ĉ����Y�҂ɕĂ�ݗ^���A���̊����ʼn��Ɋ��Z���ď�[������Ƃ������x�ł���B�������疾���ɂ����ẮA�\�o�̉��c�̐��Y����2���g�����A�Ő������}���邪�A����38�i1905�j�N�ɉ��ꔄ�������{����A��K�͂ȉ��c�������s���A���a4�i1929�j�N�ɂ�2��g���ɂ܂ŗ������B
�@���̌�A�����̉������͍H�Ɖ�����A�\�o�̉��c�͗t�^�o�R���Ɏp��ς��A����ɂ��̈ꕔ�͓��H�ɂȂ������A����9�i1997�j�N�A���ꔄ���x���p�~����A���̐����A���ʁE�̔��A�A�������R�����ꂽ���Ƃɂ��A�g���l�������ɂ�鉖�̗ǂ�����������A����҃j�[�Y�����܂�A���c�����X�ƕ��������B
�@��F�s�p�ԉƂł́A��100�̉��c����N��1.2�g���̉��Y���Ă���B�ό��q�����̑̌����Ƃ��s���u���̉w�������c���v�ł́A400�̉��c����N�Ԗ�8�g���̉��Y���Ă���B�p�ԉƂł�6��ڂƂȂ��p�҂��A���Â���Ɏ��g��ł���A�u�������c���v�ł���p�҂���q���肷��ȂǁA���@��Z�p�̓`�����s���Ă���B �@�@�@�@�@�ʐ^�@�������c��
�i3�j�����I�Ȓm�b��Z�p�@�g���l�������̍H���́A�傫��������4�H������B�S�y���̓y�̏�ɍ����܂������c�ɁA�C�����܂��A���z�̔M�Ő��������������A�����t���������������W�߁A��߂��A�����Z�x�̍����u���v�����A���Ŏϋl�߂ĉ�������B
�@�p�ԉƂł́A1��̊������̂��߂ɁA3500�`4000���b�g���̊C�������݂����A540���b�g���̂������A190kg�̐d���āA90�`100�s�̉�������B�e�H���ł́A�̂���̓`���I�ȓ���p�����Ă���B���̂قƂ�ǂ͎���ł���A��ꂽ���C���g�p����B
�\�U-4-1�@�g���l�������̐����H��
�@���R�̗͂𗘗p���邽�ߓV��ɍ��E�����g���l�������ł́A�V���ǂޗ͂��K�v�ƂȂ�B�_�̓����A�g�̌`����A�����̏������\�z���A����ł���C���̗ʂ⍻�̌���������B�V���ǂ߂�܂łɂ́A10�N���x��v����Ƃ�����B
�@�܂��A�u������3�N�A���܂�10�N�v�Ƃ�����ق��A���ߍׂ���������邽�߂ɁA�������̍ہA�̋���������Z�p���K�v�ł���B����ɁA�܂�₩�ȉ�����邽�߂ɂ́A�j�K�����������肷���Ȃ��悤�A���������Ȃ����Ƃ��d�v�ł���B�����������f��m�b�́A��ォ��`������邾���łȂ��A�l�̌o���ɂ��|���Ă����B
�i4�j���R�Ƃ̊ւ���@�l�m�́A�C�������݂ɊC�ɓ��邽�߁A���C�̕ω��ڂɊ����Ƃ�B�ߔN�A�C���̉��x���㏸���A��F�s�m�]�C�݂ł��A�܂�ɐԒ�����������悤�ɂȂ����Ƃ����B
�@�܂��A�u���c�͎R�ɂ���v�Ƃ�����悤�ɁA�Â����痢�R�Ƃ̂��������d�v������Ă����B�q�����̔R�����m�ۂ��邽�߁A�R�т������I�ɗ��p�ł���悤�A���R�̎����Ǘ����������Ȃ������B�\�o�̉��c�́A�C�ƎR���ߐڂ��Ă���A���c�̎�����̑����́A�c����R�т����L���Ă����B���c��Ƃ��I���ƁA�����̂悤�ɗ��R�ɔR���ƂȂ�d���Ƃ�ɓ���A���̒ʂ������́u���̓��v�ƌĂꂽ�B���̌�A������ɓ��錚�z�p�ނ�R���Ƃ��Ďg���悤�ɂȂ������A�ߔN�͍ĂсA�Ԕ��ނȂǂ̗��R�̎����𗘗p���邱�ƂŁA���R�̕ۑS���͂����Ă������Ƃ����g���n�܂��Ă���B
���Q�l������1�j���V���Y�i2000�N�j�w�ߑ���{���Ǝj�x�喾��
|
 |
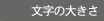     Loading
|






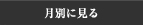
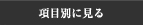
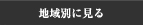
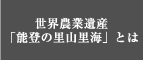
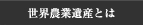




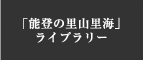

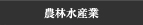
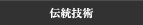

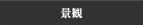
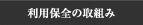
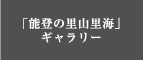


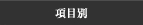


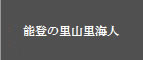
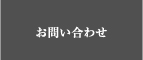






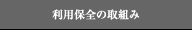
 �@
�@




![�]���X�y�[�X����](img/footer/space.jpg)